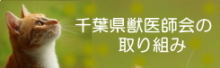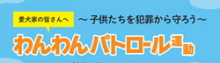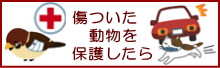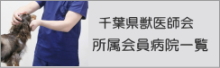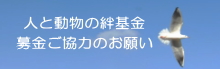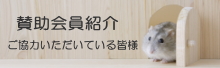HOME > ペット関連情報 >災害時の対応
|
 |
| |
| 災害時に慌てないために |
|
|
いざという時にペットと一緒に安全に避難するために
日頃から、災害に対する備えをしっかりしておきましょう。

| 日頃の備え |
1. 普段から住んでいる地域の避難場所、避難経路を確認しておきましょう。
2. 非常持出袋など、備蓄品の保管場所や、中身を確認しておきましょう。
3. 災害時に動物を避難させるためのケージや、動物のための備蓄品も
準備しておきましょう。
(ペットフード、水、予備の首輪、リード、ペットシーツ、
タオル、ブラシ、おもちゃ など)
4. 同行避難をして、避難所へ連れて行く場合を想定し、日頃から
キャリーバッグやケージに慣らしておく、むやみに吠えない、
他人、他の動物に友好的に接する、などのしつけをしておきましょう。 |
| 災害が発生したら |
1.災害時に動物を守るためには、まず飼い主が無事でいることが大切です。
落ち着いて自分と動物の安全を守りましょう。 |
| 動物の安全の確保 |
1. 突然の災害では、動物もパニックになり、いつもと違う行動をとること
があります。また、飼い主が動転していると動物にも伝わります。
出来るだけ落ち着いて行動をし、動物に飼い主の不安が伝わらないよう
にします。犬にはリードをつけ、猫は慣れたケージ等に入れましょう。 |
| 避難の際には |
1. 避難をする場合には動物も連れて避難することになりますが、
指定の避難場所においては、動物が苦手な人もいるため、周りに配慮
する事が必要となります。また、同行避難が出来ない指定場所もある
ため、事前に自治体に確認しておくことが大切です。
2. 避難所に入れない、また避難所では落ち着けないと、自家用車などに
寝泊りするケースがありますが、
狭い車内に長時間いると【エコノミー症候群】になったり【熱中症】
に陥る危険性があります。
人も動物もこまめに水分補給をしたり、運動をすることが大切です。
|
| マイクロチップの重要性 |
1. 災害時には動物と離れ離れになると、行方を探す事が非常に大変です。
動物が迷子になり、保護された時に、すぐに飼い主がわかるように
普段から連絡先を書いた迷子札や鑑札などをつけましょう。
また、個体を識別できるマイクロチップを動物に装着することは
非常に有用性があります。
大切な家族でもあるペットと離れ離れにならない対策を必ず取るように
してください。 |
 
|
|
| 活動内容 |
動物病院を探す |
ペット関連情報 |
会の活動を支える |
各種お知らせ |
獣医師会について |
負傷動物救護
傷病野生鳥獣救護
マイクロチップ
普及促進
わんわんパトロール
運動
福祉介護犬支援活動
動物愛護活動
学校飼育動物
社会科研修
実習生受入 |
会員動物病院一覧
傷ついた動物を
保護したら
傷ついた野生の
鳥獣を保護したら
|
狂犬病予防接種
ペットの病気
ペットのしつけ
災害時のペットの対応
|
賛助会員紹介
賛助会員入会案内
募金ご協力の
お願い |
学会・セミナー情報
人と動物の絆基金
アクセス
リンク
個人情報保護方針
サイトポリシー |
沿革
95年宣言
情報公開
倫理綱領
入会案内
小動物臨床分野
産業動物分野
公衆衛生分野
県獣年次学会
抄録一覧
関連資料 |
|
公益社団法人 千葉県獣医師会
〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町6-2-15
TEL 043-232-6980 |
| copyrightⒸ 2002- Chiba Veterinary Medical Association All rights reserved. |